| 2012/06/04 更新 | |||||||||||||
| <グローバル化>後の伝統工芸 2005年、「工芸の現在」と称して「今」伝統工芸の抱える課題を探るコンテンツを http://urushi-art.net に掲載してから既に8年が過ぎました。 基本的に、いまの伝統工芸が抱える課題は当時と変っていません。そして、地場産業の凋落は当時より顕在化していますし、その影響で地域の空洞化は進む一方です(実は、驚くことに首都圏も同じ状況です)。 そして、当時よりグローバル化の波は、その波頭も高く大きく押し寄せていることが肌で感ずるようになっています。そこで、続<消費>についてで発言がフリーズしていたその後を改めて続けてみたいと思います。 いきなり脈絡なくグローバル化を語っても混乱するだけですので、ここは先ず「工芸」にとってグローバル化とは、何を意味するのかから始めたいと思います。 先ず、グローバル化に先だって、僕らが生活している謂わば高度資本主義社会とは、どんな社会かと言うことを再確認してから話を進めたいと思います。これは続<消費>についての前の項で触れていますので、詳しくは、そちらを参考にして頂いて、ここでは基本を押さえたいと思います。 |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
 i-phone |
|||||||||||||
| 高度資本主義社会とは・・・・・・
(1)消費はもはやモノの機能的な使用や所有ではない。 |
|
||||||||||||
 (videonews.com より) |
|||||||||||||
|
藻谷 浩介もたに こうすけ
(日本政策投資銀行参事役)
|
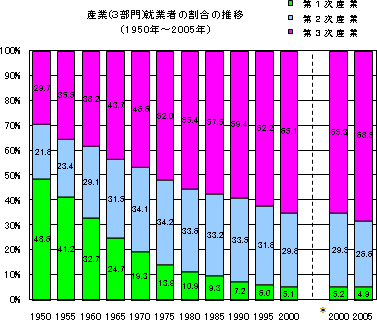 (統計局ホームページより) |
<グローバル化>とは・・・・ 社会的あるいは経済的な連関が、旧来の国家や地域などの境界を越えて、地球規模に拡大して様々な変化を引き起こす現象である。(Wikipediaより) |
|||||||||||
|
マル激トーク・オン・ディマンド 第497回(2010年10月23日)
データで見る日本経済の本当の病状
ゲスト:藻谷浩介氏(日本政策投資銀行参事役)
経済学者でもない、金融機関の地域振興担当者が書いた本がバカ売れに売れているという。日本政策投資銀行の藻谷浩介氏が書いた『デフレの正体』だ。
藻谷氏の論点は明解だ。日本経済に影響を与える因子は数多あるが、少なくとも戦後一貫して日本経済に最も大きな影響を与えたファクターは、団塊の世代の動向だった。団塊の世代と団塊ジュニアの2つの大きな山が明らかにいびつな「人口の波」を形成している。そして、その波の動きが他のすべての要因を飲み込むほど激しい影響を日本経済に与えてきたこと、そしてこれからますます激しい影響を与えることを、データが雄弁に語っている。だからこそ、あらゆる経済対策はまず、その「人口の波」をいかに乗り切るかに主眼を置いたものでなければ、効果は期待できないというものだ。 藻谷氏は日本経済について、実際のデータを読まず、現場を見ない人によって、不正確な指摘が行われている場合が多いと言う。そもそも診断が間違っているのだから、当然、処方箋も的外れなものになる。「人を減らして労働生産性を上げる」、「経済成長を達成する」、「ものづくり技術の革新」など、一見もっともらしい主張は、誤診からくる的外れな処方箋だとして、藻谷氏はこれらを一蹴する。 誤診の典型として、藻谷氏は莫大な人口と安い労働力を持つ中国の経済成長が、日本の脅威となっているとする「中国脅威論」をあげる。これもデータを見れば一目瞭然だが、中国の経済成長によって日本の高級品を求める中国人富裕層人口が増え、日本からの輸出が増えたため、日本の対中貿易黒字は増加した。日中の経済関係は、中国が栄えれば栄えるほど、より日本が儲かる構造になっているのだ。そのため、中国の台頭は恐れることでも妬むべきものでもなく、むしろ日本はありとあらゆる手段を使って、中国でモノを売れる平和な関係を維持し、これからも億単位で増える中国の富裕層が欲しがる、ブランド力を持った商品を作ることに注力することが賢明だと、藻谷氏は言う。 同じことが、韓国やシンガポールについても言える。また、アメリカ、イギリス、ドイツに対しても、日本は貿易黒字国である。 しかし、一方で、日本が常に貿易赤字を抱える国がある。それがフランスとイタリアとスイスだと言う。日本はブランド力でこれらの国々が持つ超一流ブランドに勝つことができていない。つまり日本が目指すべき道は、中国などの新興国の安売り攻勢にコストカットで立ち向かうのではなく、新興国が富めば富むほどより多くの人に欲しがられる、シャネルやフェラーリやロレックスに匹敵するブランド力のある商品を開発することにある。藻谷氏は日本は「高級品ばかり売る宝石屋」だと言う。 予断を持たずにデータを見ることが重要と説く藻谷氏が指摘する日本の大問題が、まさにこれから激動が始まる「人口の波」だ。1945〜50年の5年間に、約1100万人の日本人が生まれた。いわゆる「団塊の世代」だ。日本経済の転機は、ほぼ例外なくこの世代の人々の行動によって引き起こされてきたことが、データから見て取れる。この世代が就労年齢に達し労働人口が一気に増えたことで高度経済成長が起き、この世代が家を持つ年齢に達した頃に住宅バブルが起きる。 そして、昨今の日本の経済停滞も、この人口の波の移動によって引き起こされていると藻谷氏は説く。02年〜06年の戦後最長の好景気で日本は輸出を大幅に増やし、それによって高齢富裕層の個人所得は増加した。しかし、老後の不安を抱える高齢者は、積極的な消費は行わない。そのため輸出は増加するが、内需が一向に拡大しない。それが、大半の日本人が景気拡大の恩恵に浴することができない理由だったと藻谷氏は言う。 消費が落ち込んでいるにもかかわらず過剰な生産が続くと、在庫が増え価格競争が激しくなる。その結果、商品やサービスの価格は下がる。そう考えると、今起きているのはデフレではなく「ミクロ経済学上の値崩れ」ではないか、これが、藻谷氏の主張する『デフレの正体』だ。 景気の循環をも飲み込む「人口の波」は、今後も深刻な問題を引き起こし続ける。一番の問題は、今まさに団塊の世代が就労年齢を過ぎ、労働人口が急激に減ること。そして、それが近い将来、一斉に要介護年齢に達することだ。団塊世代の大半が要介護年齢に達する頃に、今度は団塊ジュニア世代が引退の年齢を迎え始める。その2つの大きな山を、それより遙かに少ない労働人口が支えていかなければならない。これが今日の日本経済が抱える最大の課題だと、藻谷氏は言う。 そうした試練を乗り越えるための秘策として藻谷氏は、高齢者から若者への所得移転、女性の就労や経営参加の推進、外国人観光客や短期定住者の招来の3つをあげるが、果たして日本はそれを実現できるのだろうか。(videonews.com より抜粋) インターネットラジオ videonews.com は、525円/月でご覧になれます。 |
|||||||||||||
| 問題が大きくて中々前に進みません。 続けます。 要するに、産業の構造改革なしに古い業態で新興国と闘っても、賃金の低い新興国には価格競争で負けてしまう・・・・このことを工芸に当てはめるとどうなるのか。 その回答は、左の欄で紹介する藻谷浩介著「デフレの正体」に詳しくに述べられています。ただ、工芸に限定して述べられている訳ではないので、ここでは成るべく工芸の枠内で話を進めてみたいと思います。 |
|||||||||||||
 |
|||||||||||||
| 先日、目黒に出来た新しいgalleryで、ちょっとした集まりがありました。伝統工芸と関わりがある部署から経産省の次長・課長など三人のお役人が見えました。常滑の晴鳶堂こと中野さんも他の用事も兼ね上京して参加し、他にもこのgalleryに関わりのある作家や建築事務所の方も含め15人ほどで、それなりに盛り上がりました。 一応名目は「現場を聞く会」ということでしたが、経産省がそもそもどう言った仕事をこなしているのか分らないので、とにかくアットランダムに気に掛かることを述べ合うというスタイルで会は進みました。初顔合わせでもあったので、さして面白い生産的な話が出たわけでもありませんでしたが、こういった会を続けて行けば課題もはっきりとして会もそれなりに意義深いものになって行くかも知れません。 会を終えて、僕なりに見えてきた課題が、このページに重なるところも多いので、そこでのレポートを紹介したいと思います。ちょっと堅いのですがご勘弁を。 日本現代工芸の課題と戦略 基本、工芸は、前近代の生産システムを引きずっているので工業とは違った再生法がとられるべきですが、一次産業であろうが二次産業であろうが、これからの先進諸国がアプローチしなければならない手法は共通しています。 こういった状況の中で、手間の掛かる工芸品を制作するとしたならば、正当な価格を設定しなければ生活を含めて成り立ちません。その意味でも付加価値=ブランド化が急務です。 そして、その戦略とは・・・・ |
|||||||||||||
 |
|||||||||||||
| <作家という有り様> ○マーケットに逆立する心的構造をもつ ○お金で判断出来ない、あるいはお金に還元できない精神領域があるとする姿勢でものを作るスタンス これ↑このページで述べたいことのラフスケッチのようなもので走り書きです。今の社会の前にあった、つまりグローバル化が顕著になる以前の社会で、工芸家やアートを志向する人間のメンタリティーを抜き出したものです。 |
今中国では、新生「景徳鎮ブランド」の陶板が富裕層の中で飛ぶように売れているそうです(常滑の関係者が現地で確認した情報です)。内容は、1m位のサイズの凸凹のリリーフに、あまり面白くもない具象が描かれていて、もの凄い高値で売れているという状況です。でも、やがてこれにも飽きるのは目に見えていて、次は、モダーンなものへ嗜好は移ってゆくのは間違いありません。 彼らの過去150年は、植民地化、侵略化の中にあったので、日本が受けた近代の洗礼が抜け落ちています。それ故、彼らの手でモダーンを表現することは、非常に難しいのではと思います。なので、そこを彼ら中国と同じDNA(出自)をもつ純欧米ではない、東洋と西洋を統合する術をもった日本が、抜け落ちた歴史を埋め合わせる、あるいは補完することで、彼らの歴史的な宿命として持ってしまった「欠如」を埋める役割を担えるのではないでしょうか。 この先、お隣中国では、モダーンで抽象的な嗜好が確実に求められて行くと思います。日本としては、その先に来るであろうポストモダンまで見据えた戦略を、今起てなければならないと思います。 <戦略 1> 抽象的な作品は、それが優れた作品かどうかの根拠を示すのが難しいので、もし中国で展開する場合、その作品の水準を示す、謂わば「箱書き」のような“お墨付き“がどうしても必要になります。モダンアートに限定すると、そのお墨付きは、欧米、特にEUでの評価・・・・となります。従って、中国での展開を成功させるには、先ずそれに先だってEU での実績が欠かせない条件になるはずです。 但し、日本の文化を比較的好意的に理解する下地のあるEU諸国は、今ギリシャ問題を含め難しい局面を迎えています。従って、そこでのマーケットには期待出来ません。つまり充分に“売れる”ことは先ず考えられません。重要なのは、EUで売れることではなく、EU
でグループ展なり、個展など、所謂展覧会をした“実績”です(もちろん売れるにこしたことはありませんが・・・)。 先ずは、EU で展覧会を持ち、そのあとそれを引っさげて中国に打って出るこという順番が必要です。中国での展開に失敗しないようにするには、この様な前段が欠かせないように思います。
これは、現代美術界の村上隆が、アメリカでとった戦略と重なる手法です。モダーンの発祥は、欧米なので、その地での実績は、東洋での展開にはどうしても必要になります。
<戦略 2>
日本文化や“日本製“は、それそのものがブランドになり得るので、問題はどの様にその”物語“あるいは”神話“を作るか・・・に掛かっています。その一つは、ヨーロッパに於いて嘗て起きたジャポネスクのムーブメントです。特に欧州において”日本趣味“は、インテリの隠れたステイタスでもあります。 |
||||||||||||
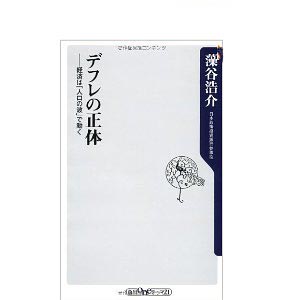 ここを↑↑クリックすると藻谷浩介さんんのコメントが聴けます |
|||||||||||||
| どうして一工芸家が、こんなややこしい経済問題に触れなければならないのか・・・・正しくグローバル化とはそういった事態を指します。つまり日本ばかりでなく、世界の経済動向を見ずに、自分の作りたいものを脳天気に作って生活が回る世の中ではなくなってしまったからです。僕自身本当は、作家ではなく職人になりたかった訳です。でも残念ながら、日本の社会は、近代化の中で総てが大きく変りました。それまであった生活様式は、新しい生活には馴染まず、僕らの周りは、もの凄い勢いであらゆるものが変って行きました。もちろん、工芸も例外ではありませんでした。 裸電球の下、難しい顔をして黙々と夜なべを続ける職人の姿は、もはやイメージの中だけにしか存在しません。様式美を失う前の社会では、それまで綿々と続いてきた手順にのっとって仕上がったものを、これまた綿々と続いてきた流通に流せれば良かった訳です。職人は、毎年巡ってくる歳時に沿って、人びとが待ち望む定番を、その約束事に身を委ねて作り続けることで充分でした。 今はまったく違います。毎年の歳時に備えて企画を担った問屋も価格競争の中で消え、もはや作り手自らが新しく登場した社会に向けて新商品を提案する時代となりました。こうなると職人の定義そのものも変らざるを得ません。 僕の職人の定義は「既定の流通に向けて請け負った手仕事を仕上げ流す職業従事者」を指します。そして、今では既定の流通そのものが縮小あるいは消滅してしまったので、職人という有り様それ自体が消えかかっていると言えます。 |
|||||||||||||
 江戸の職人 川越三芳野天神縁起絵巻(部分) 五代川越城主・松平伊豆守信綱の寄進と伝えられる。江戸初期、17世紀半ば頃のもの。 (「絵図 大工百態」((株)新建築社刊)より) |
|||||||||||||
| 上の画像は、江戸の職人達の作業風景です。当時の腕良い職人像とは、頑固で拘りがあり、決して自分を曲げない一徹者・・・・こういった姿勢は今でも、ものを作る上で必要なメンタリティーだと思いますが、ただ、ひとつ間違えればまったく頓珍漢なものを自己満足で作り続けた末に在庫が溢れてアウトと言うリスクと背中合わせでもあります。 グローバル化で僕らのプラットフォーム(社会基盤)は大きく変りましたし、今後も変わり続けると思います。こういった社会変動が常態化した世界では、何に対して「頑固で拘りがあり、決して自分を曲げない一徹者」なのかが重要になります。当然、以前の様式美は殆ど陳腐化しているので、新しいデザインを提案しなければならないですし、それを生み出す努力も尋常ではないと思います。大変な世の中になってしまった訳ですが、これはもの作りの世界だけに言えることではありません、総ての業種に当てはまる大変さでもあります。 |
|||||||||||||
  江戸の左官 |
|||||||||||||
| ・・・・・・つづく | |||||||||||||
